
【参議院本会議:大門実紀史議員の質問と政府の回答(Q&A形式)】
1. 税の基本的な考え方について
Q.(大門議員)
社会保障や教育は「助け合い活動」なのか?それとも、憲法に基づき政府が保障すべき国民の権利なのではないか?
「税は回避」との表現は誤りではないか?税の本質は応能負担(所得に応じた負担)ではないか?
財務省の考えは、「受益者負担(応益負担)」へと変質していないか?
A.(加藤財務大臣)
税は「公的サービスの費用を皆で分かち合うもの」であり、応益負担の要素もあるが、応能負担の考え方も重要。
「社会での助け合いのための活動」という表現は、「自助・共助・公助の適切な組み合わせ」を意味するもの。
少子高齢化やグローバル化を踏まえ、公平で中立的な税制を目指している。
2. 応能負担 vs. 応益負担の問題
Q.(大門議員)
近代民主国家の税制は「応能負担」が原則。政府の方針は「応益負担」へと変質していないか?
「税は受益者が負担すべき」という考え方は、庶民増税を正当化し、所得再分配を妨げるものではないか?
石破総理は「税の応能負担より、応益負担を重視すべき」と考えているのか?
A.(石破総理)
「応益負担を重視しているわけではない」。
社会保障給付などを考慮すると、低所得者ほど手厚い支援を受けることになるため、税と社会保障の給付を総合的に評価すべき。
公共サービスの給付と負担のバランスを取ることが重要。
3. 1億円の壁(金融所得課税)の是正
Q.(大門議員)
株式売却益や配当への課税(金融所得課税)が低く、富裕層ほど税負担が軽い「1億円の壁」を放置しているのではないか?
アメリカでは金融所得には重い税が課されている。日本も富裕層への課税を強化すべきではないか?
A.(石破総理)
令和5年度税制改正で「極めて高い水準の所得」に追加的な負担を求める措置を導入。
しかし、日本の金融市場や投資環境も考慮しながら慎重に対応していく。
4. 課税最低限の引き上げ
Q.(大門議員)
日本の課税最低限(285万円)は欧米諸国(ドイツ:484万円、アメリカ:892万円)に比べて低すぎる。
なぜ課税最低限を引き上げてこなかったのか?
なぜ「公的サービスを賄うために国民全体で負担するべき」という理屈を持ち込むのか?
A.(加藤財務大臣)
課税最低限は「整形費の観点」や「公的サービスの費用を広く分かち合う必要性」などを総合的に考慮して決定。
物価が上昇していなかったため、1995年以来見直しが行われてこなかった。
今回、課税最低限を160万円に引き上げる方針。
5. 消費税の減税
Q.(大門議員)
消費税は逆進性が高く、庶民に大きな負担を強いている。
そもそも消費税は「大企業・富裕層減税の穴埋め」として導入されたものであり、社会保障の財源として適切ではない。
消費税を5%に減税すべきではないか?
A.(石破総理)
消費税は「社会保障財源として必要」との立場。
社会保障給付を考慮すると、低所得者に手厚い仕組みになっており、単純な税負担の議論ではない。
6. 高額医療費負担の引き上げ
Q.(大門議員)
高額療養費制度の負担額引き上げは、がん患者などの生命を脅かす。
物価高騰で生活が圧迫される中、負担の引き下げこそ必要ではないか?
患者団体の意見を反映し、負担上限額の引き上げを撤回すべきではないか?
A.(石破総理)
高額療養費制度の見直しは秋までに方針を決定する予定。
保険料負担の抑制や制度の持続可能性を考慮するが、負担上限の引き下げは検討していない。
7. 企業・富裕層への税負担強化
Q.(大門議員)
アベノミクスによる株価上昇で富裕層は利益を得たが、それに対する課税が不十分ではないか?
「税の公平性」の観点から、儲かっている大企業や富裕層により多くの負担を求めるべきではないか?
A.(石破総理)
令和7年度税制改正で法人税率を引き上げる方針。
ただし、ターゲットを絞った政策対応を実施し、投資環境を損なわないように配慮する。
まとめ
大門議員の主張:
税の本質は「応能負担」なのに、政府は「応益負担」にシフトしている。
庶民増税(消費税・課税最低限の引き下げ)は富裕層優遇の結果。
高額療養費負担の引き上げは撤回し、富裕層・大企業に対する課税を強化すべき。
政府の回答:
「応能負担も考慮しているが、社会保障の給付も含めてバランスを取るべき」との立場。
「1億円の壁」や法人税の見直しには取り組んでいるが、投資環境への影響も慎重に考慮。
高額療養費負担の引き上げは「制度の持続可能性」を理由に維持。
→ 税制改革における「庶民負担 vs. 富裕層・大企業の負担」という構図が明確に浮かび上がった本会議となった。
応能負担と応益負担について
税制度には「応能負担」と「応益負担」という2つの基本的な考え方があります。これらは、誰がどのように税を負担するべきかを決める重要な基準となります。
応能負担 は、「負担能力に応じて税を支払う」という考え方です。経済的に余裕のある人がより多くの税を負担する仕組みで、所得税や相続税、法人税などがこれに該当します。所得が高いほど税率が上がる累進課税は、その代表例です。この仕組みにより、所得格差を是正し、社会全体の公平性を保つことが期待されています。
一方、応益負担 は、「受けた利益に応じて税を支払う」という考え方です。消費税や高速道路の利用料金、健康保険料などがこれにあたり、サービスを利用する人がその分の費用を負担する仕組みです。応益負担の考え方は、特定のサービスを利用しない人の負担を軽減し、財政の効率的な運用を図ることができます。
現在の日本の税制では、応益負担の比重が増し、消費税の増税や社会保険料の引き上げなどが進んでいます。一方で、累進課税が適用される所得税や法人税の負担は相対的に軽減される傾向にあり、「応能負担と応益負担のバランス」が大きな課題となっています。特に、低所得者にとって消費税などの負担が重くなる一方で、富裕層の税負担が軽減される「1億円の壁」などの問題も指摘されています。
税制の公平性を保つためには、応能負担と応益負担の適切なバランスを維持することが求められます。どの層にどの程度の負担を求めるべきか、今後の税制改革の動向に注目が集まっています。
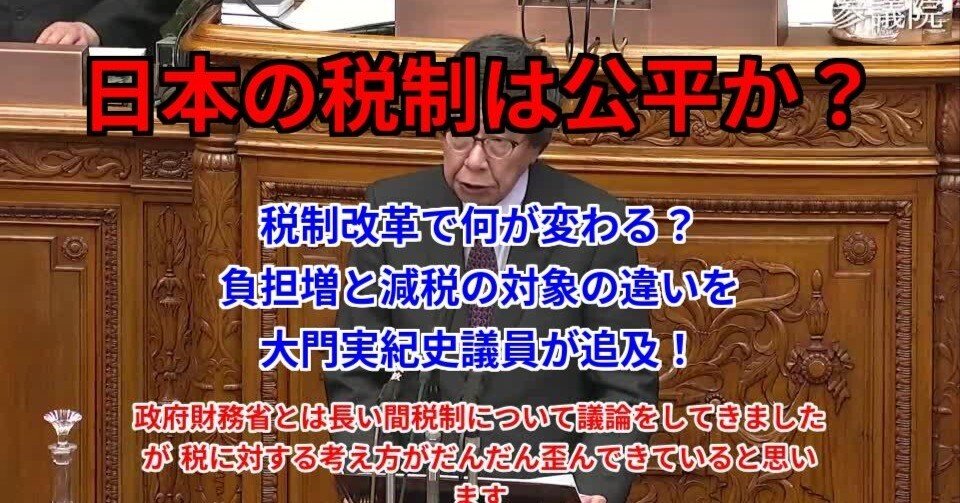


コメント